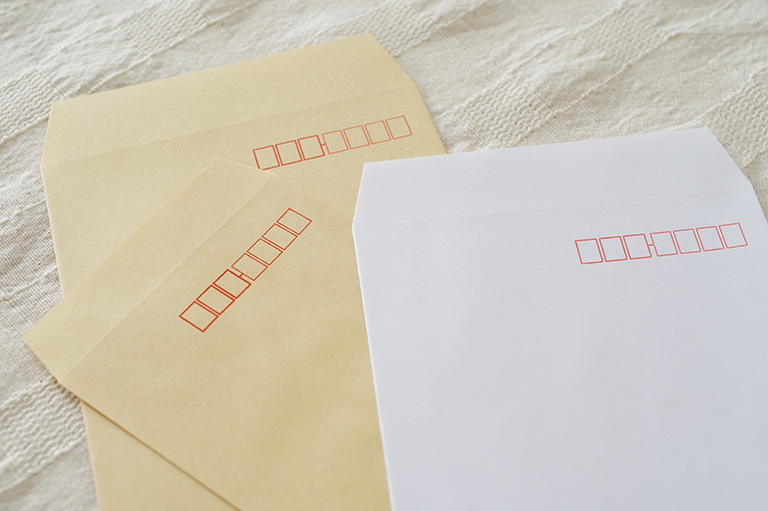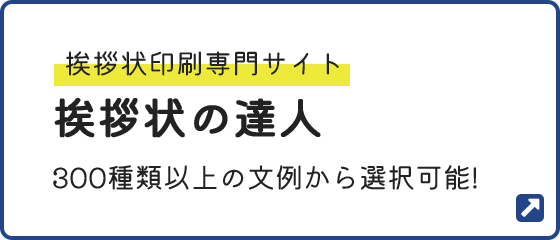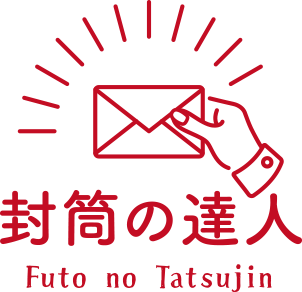多くの企業では、自社の社名や住所が入ったオリジナルの封筒を作成しています。会社のロゴを配し、会社のカラーを反映させたオリジナル封筒を作成すれば、封筒を受け取った相手は一目で差出人を連想することが可能です。さらに、オリジナル封筒にはブランディングの効果もあることから、多くの会社では封筒印刷でオリジナルの封筒を作成しています。
オリジナルの封筒印刷を初めて作成する際には、どんなサイズの封筒を作成すべきか悩むケースもあるかもしれませんが、初めてオリジナルの封筒印刷を発注するのであれば、使用頻度の高い長3封筒がおすすめです。
今回は、長3封筒をおすすめする理由や長3封筒印刷のサイズや料金相場まで詳しくご説明します。
長3封筒とは?サイズ・用途・特徴を解説

長3封筒は、どのような封筒かご存じですか?まずは、長3封筒のサイズや用途、特徴などから解説します。
長3封筒のサイズと対応用紙
長3封筒とは、長形3号と呼ばれる長形封筒の一つであり、長3封筒のサイズは、横が120mm、縦が235mmです。短辺に封入口がある、縦に長い形をしており、A4サイズの用紙を三つ折りにしてきれいに封入することができます。そのため、長3封筒はビジネスシーンでは最も利用頻度の高い封筒サイズだといわれています。
長3封筒の主な用途
長3封筒は、A4用紙を複数枚、封入できるサイズであることから、長3封筒の用途は非常に幅広くなっています。請求書や見積書を送付する場合はもちろん、ダイレクトメールを発送する際にも、長3封筒は利用されるケースが多いのです。
加えて、長3封筒は定形郵便として送付できる最大のサイズでもあります。A4サイズを封入できる封筒には長3封筒のほかにもあります。しかし、定形郵便の料金で複数枚のA4用紙の書類を送付するとなると、長3封筒の使い勝手が非常によいのです。
長形3号と他サイズ(角2など)の違い
封筒にはさまざまなサイズがあります。
長形3号より一回り小さい、長形6号(長6封筒)もA4用紙を四つ折りにして封入できるサイズです。長6封筒のサイズは、横が110mm、縦が220mmです。長6封筒も定形郵便で送付できるサイズですが、長3封筒に比べると縦も横もわずかに小さいため、A4用紙を複数枚重ねて封入することはできません。そのため、A4用紙を複数枚封入できる長3封筒を活用する企業の方が多くなっています。
また、角形2号(角2封筒)もA4用紙を送付する際に活用されることの多い封筒です。角2封筒のサイズは、横が240mm、縦が332mmで、A4用紙を折らずにそのまま封入できる大きさになっています。履歴書や契約書など、折り目を付けずに送付したい書類を封入する際に用いられることの多い封筒サイズです。さらに、横210mm、縦297mmのA4用紙よりも余裕のあるサイズとなっているため、厚みがある書類やパンフレットなども封入しやすくなっています。
そのほか、洋形0号(洋0封筒)もA4用紙を三つ折りで封入することができます。洋0封筒は、横が235mm、縦が120mmで、長3封筒を横にしたときと同じ大きさです。長辺に封入口がある封筒を洋形封筒といい、洋0封筒は、長3封筒と同じサイズであることから洋長3封筒と呼ばれることもあります。
封筒の色は企業イメージにどう影響する?
オリジナルの封筒印刷を発注する際には、封筒の色も自由に選ぶことができます。例えば、会社のロゴに合わせた色やコーポレートカラーを採用すると、統一感のある印象を与えることができるでしょう。さらに、名刺やホームページの色合いなどとも統一すると、より洗練された印象になります。
また、色は、見る人にさまざまな印象を与えるものです。そのため、会社が目指す方向性に合った色の封筒を選ぶと、会社のイメージを印象付けやすくなります。
例えば、白いケント紙を使った封筒の場合、清潔感や誠実さを印象付け、企業の信頼性アップにつながるでしょう。淡いパステルカラーを使った封筒の場合は、柔らかい印象や親しみやすい印象を与えることが可能です。反対に、ネイビーやグレーなど、落ち着いた色合いを選ぶと、高級感があり、スタイリッシュな雰囲気を演出できます。そのほか、未晒しのクラフト紙の封筒を選択する企業も少なくありません。クラフト紙の場合、実務的なイメージやコスト重視のイメージなどがありました。しかし、近年では、漂白剤を使用しない、自然な風合いがSDGsに注力する企業姿勢のアピールにもつながるため、ナチュラルな雰囲気が漂うクラフト紙を選ぶケースも増えています。
長3封筒印刷の種類と選び方
長3封筒印刷の発注をする際には、印刷する部数だけでなく、印刷用紙やその他のオプション事項も選択が可能です。納得できるオリジナルの長3封筒を作成するために知っておきたい長3封筒印刷の種類や選び方をご説明します。
封筒の素材の種類と選び方|ケント紙・クラフト紙
封筒の色は、企業の印象を左右するとご説明しましたが、封筒印刷をする際には封筒の色だけでなく、素材から選ぶ必要があります。まず、ケント紙は、非常に滑らかで、高い白色度を誇る美しい用紙です。表面が滑らかなため、インクが滲みにくく、美しい封筒印刷ができます。白色を基調にした高級感溢れる、格調高い封筒を作りたい場合は、ケント紙がおすすめです。
また、クラフト紙は化学パルプから作られた紙で、繊維が長く、薬品での漂白処理もしていないため、破れにくい、強度の高い用紙です。ナチュラルな雰囲気を演出したい場合やコストを抑えたい場合などは、クラフト紙を選択するとよいでしょう。
そのほか、色付きのカラーペーパーやカラークラフト紙を選択できるケースもあります。
印刷方式の種類とそれぞれの違い|オフセット印刷・オンデマンド印刷
印刷方式には、オフセット印刷とオンデマンド印刷の2種類があります。オフセット印刷は、版を作り、シアン、マゼンダ、イエロー、ブラックの4つのインクを刷り重ねることで色を再現する印刷方式です。版に付けたインクをブランケットと呼ばれるゴム版に乗せ、ブランケットから紙に転写する印刷手法で、版を作る時間や手間はかかるものの、多くの部数を発注する場合にはオフセット印刷の方が価格を低く抑えられます。
一方、オンデマンド印刷とは、版を作らず、デジタルデータをそのまま印刷する手法です。版を作らないため、スピーディーに印刷ができ、少部数からでも対応できるというメリットがあります。しかしながら、まとまった部数の封筒印刷を行う場合は、かえってコストが高くなってしまう点はオンデマンド印刷のデメリットです。
封筒の仕様の特徴と使い分け|窓付き・のり付き・透け防止など
封筒には、さまざまな機能を備えているものもあります。封筒印刷を依頼する際は、利用目的に合わせて、自社に合った機能をもつ封筒を選ぶことが大切です。
例えば、長3封筒を使って請求書を送付したり、ダイレクトメールを送付したりする機会が多い場合などは、窓付き封筒が便利です。窓付き封筒とは、宛名部分に透明な窓が付き、内側に印刷されている宛名が見えるようになった作りになっている封筒です。送付時に宛名を書いたり、宛名ラベルを印刷して貼付したりといった手間がかかりません。また、窓付き封筒を利用すると封入物と宛名が異なってしまうといったミスを防ぐこともできます。
さらに、大量に発注する場合などは、封入口にのりやテープが付いた封筒を選ぶと、封緘の手間を大幅に軽減することが可能です。
そのほか、個人情報など、重要な情報を記載した書類を送付する場合、薄い色の封筒を使用すると中身が透けて見える恐れがあります。機密情報を送付する際には、透け防止加工がなされた封筒を選ぶと、安全に書類を送付することが可能です。また、透け防止封筒を活用することで、慎重に情報の取り扱いをする企業というイメージを与えることもできるでしょう。
長3封筒印刷を発注する際には、自社の利用シーンに合わせて適切な仕様を選ぶことが大切です。また、窓付き封筒やのり付き封筒、透け防止封筒などを選ぶとコストは高くなるため、複数種類の長3封筒印刷を行い、必要に応じて使い分けをしてもよいでしょう。
長3封筒印刷の料金相場と確認ポイント
長3封筒印刷は、選ぶ用紙や印刷部数、封筒に備わった機能などによって料金が変わってきます。では、長3封筒印刷料金の相場はどのくらいなのでしょうか。また、発注時に確認しておきたいポイントについてご説明します。
印刷枚数ごとの料金目安
ケント紙に片面1色で封筒印刷をする場合の料金の目安は100部で2,000円~3,000円程度、500部で5,000円~6,000円程度、1,000部で8,000円~9,000円程度です。
印刷会社によっては、封筒印刷の部数が増えると、オフセット印刷で対応するようになるため、印刷部数が大きくなるほど1枚当たりの単価は安く抑えられます。そのため、長3封筒の使用頻度が高い場合は、まとめて封筒印刷を発注した方がコストを抑えられるでしょう。
納期の目安と急ぎ対応の可否
印刷会社によって納期は変わるため、封筒印刷を依頼する際には、納期の目安も確認することが大切です。また、印刷会社の中には、急ぎの納期に対応しているケースもありますが、急ぎ仕上げの場合は料金を高めに設定しているケースも少なくありません。急ぎ対応の可否を確認すると同時に、急ぎで依頼した場合に料金がどのくらい変わるのかについても事前に確認しておきましょう。
送料・支払い方法などの確認ポイント
封筒印刷の料金は安くても、送料が高いケースもあります。また、急ぎの場合などは、支払い方法のバリエーションが豊富な方が発注しやすいでしょう。そのため、長3封筒印刷を発注する際には、送料や支払い方法などについても事前に確認しておくことが大切です。
長3封筒印刷会社の選び方
長3封筒印刷を発注する際の印刷会社の選び方のポイントを3つご紹介します。
料金・品質・対応のバランスをチェック
封筒印刷に対応している印刷会社は多数あります。しかし、それぞれ、提供しているサービス内容や印刷品質、料金は変わってきます。印刷料金が安い印刷会社の場合、入稿されたデータを確認することなく、そのまますぐに印刷工程に進むケースもあります。その場合、校正データをチェックするステップがないため、誤字があった場合でもそのまま印刷がなされてしまいます。また、色合いのチェックをすることもできません。
そのため、長3封筒印刷を発注する際には、料金の安さだけに注目するのではなく、印刷品質や対応のバランスをチェックし、納得できる印刷会社を選ぶようにしましょう。
テンプレートの有無・入稿形式を確認する
封筒印刷を受け付けている印刷会社の中には、長3封筒のデザインを簡単に作成できるテンプレートを用意しているところがあります。テンプレートがある場合、大きさも指定されているため、手間をかけずに長3封筒サイズに合わせたデザイン作成が可能です。
また、デザインデータの入稿形式が指定されている場合もあります。Illustratorなどのデータのみ扱う場合、Illustratorのソフトがなければ入稿することができません。Office系ソフトで作成されたデータは文字化けの可能性があるため、非対応の印刷会社もありますが、PDFデータなら入稿できるところも多いです。Office系ソフトもしくはPDFでの入稿が可能であるかもチェックしましょう。
発注時にはテンプレートが用意されているかどうか、入稿形式にどのような指定があるのかについても確認することが大切です。
法人アカウント・後払いに対応しているか
最後に、法人アカウントと後払いに対応しているかどうかも重要なチェックポイントとなります。法人アカウントの取得ができない場合、再注文をする際に、再びデータを入稿しなければならず、発注履歴の管理もできません。継続的に長3封筒印刷を依頼する予定があれば、法人アカウントを取得できる印刷会社を選んだ方がよいでしょう。
また、印刷会社の中には、後払いには対応していないところもあります。月締め請求やNP掛け払いなど、後払い決済に対応しているかも事前に確認することをおすすめします。
長3封筒印刷のデザインと入稿の注意点
長3封筒デザイン作成時のポイントと入稿時の注意点をご説明します。
よく使われるデザインとは?ロゴ・社名・差出人など
長3封筒印刷時には、ロゴ、会社名、住所、電話番号、メールアドレス、ホームページのURLなどを記載するケースが多くなっています。会社ロゴを入れると、受取人は、差出人名を確認することなく一目で送付元を判断できるようになります。さらにロゴが無意識に目に入ることで、会社のブランディングにも効果的です。長3封筒では、社名を大きく記載し、その右にロゴ、下に住所、電話番号、ホームページURLなどを配置するデザインが多くなっています。
データ入稿時のチェックポイント
データを入稿する際には次のような点をチェックしましょう。
・推奨されているファイル形式・バージョンに適合しているか
・Illustratorの場合、フォントのアウトライン化やレイヤー整理をしているか
・カラーモードがCMYKになっているか
・ロゴ画像の解像度は指定されたものになっているか
・塗り足しや余白を設定しているか
テンプレートの活用と注意点
テンプレートを活用すると、デザインの知識がなくても、簡単に封筒デザインを作成できます。しかしながら、テンプレートに記載されているガイドのラインや説明文などを削除しない場合、そのまま印刷されてしまう恐れがあるため、確実に削除するよう注意が必要です。また、印刷可能範囲も確認し、実寸サイズとずれがないかもチェックしておくようにしましょう。
まとめ:長3封筒印刷は用途に合わせて賢く選ぼう
長3封筒はビジネスシーンで最も活用しやすい封筒サイズだといわれています。そのため、初めてオリジナルの封筒印刷を発注するのであれば、長3サイズを選ぶとよいでしょう。
長3封筒を作成する際には、封筒の色やインクの色などによって相手に与える印象が変わります。コーポレートカラーに合わせたり、色の心理的効果を利用したりしながら、演出したいイメージを伝えられるような長3封筒を作成しましょう。
また、長3封筒には、窓付き封筒やのり付き封筒、透けにくい封筒などもありますが、機能付き封筒の場合、単価は若干高くなります。そのため、長3封筒印刷を行う際には、封筒の使用目的に合ったものを選ぶことが大切です。
長3封筒に関わらずですが、企業カラーやイメージカラーを封筒の色に採用するのは印象的になる一手です。
例えばロゴのベースカラーに青色を使用しているのであれば、色系統のマッチを見越して水色の封筒を使用してみるのもいいと思います。
ロゴも含めて印字色を同系統にまとめる方法は、デザインする際に統一感を出すための効果的な方法のひとつです。
近い色同士を組み合わせたり、同じ色合いで明度や彩度に変化を付けて入れ込んだりと、デザインにおいて大事な「統一感」という面では使いやすい手法だと思います。
カラー封筒を使用することは、取引のあるクライアントさんやDMなどを定期的に送っている方々へ届いた時点で「あそこから届いた封筒だな」という色の視認性でこちらを認知させることも狙える方法です。
また逆に、封筒の色と正反対の色合いでデザインする手法もあり、この場合はお互いの色を引き立て合うので視覚的インパクトが強くなります。
しかしながらアクセントやメリハリをつけてインパクトを与える方法でもあるので、送る相手や印象も考慮した方がいい手法でもあると思います。
いずれにしても、使用用途やコストなども含めて包括的に封筒の仕様は決定すべきです。
■監修者プロフィール
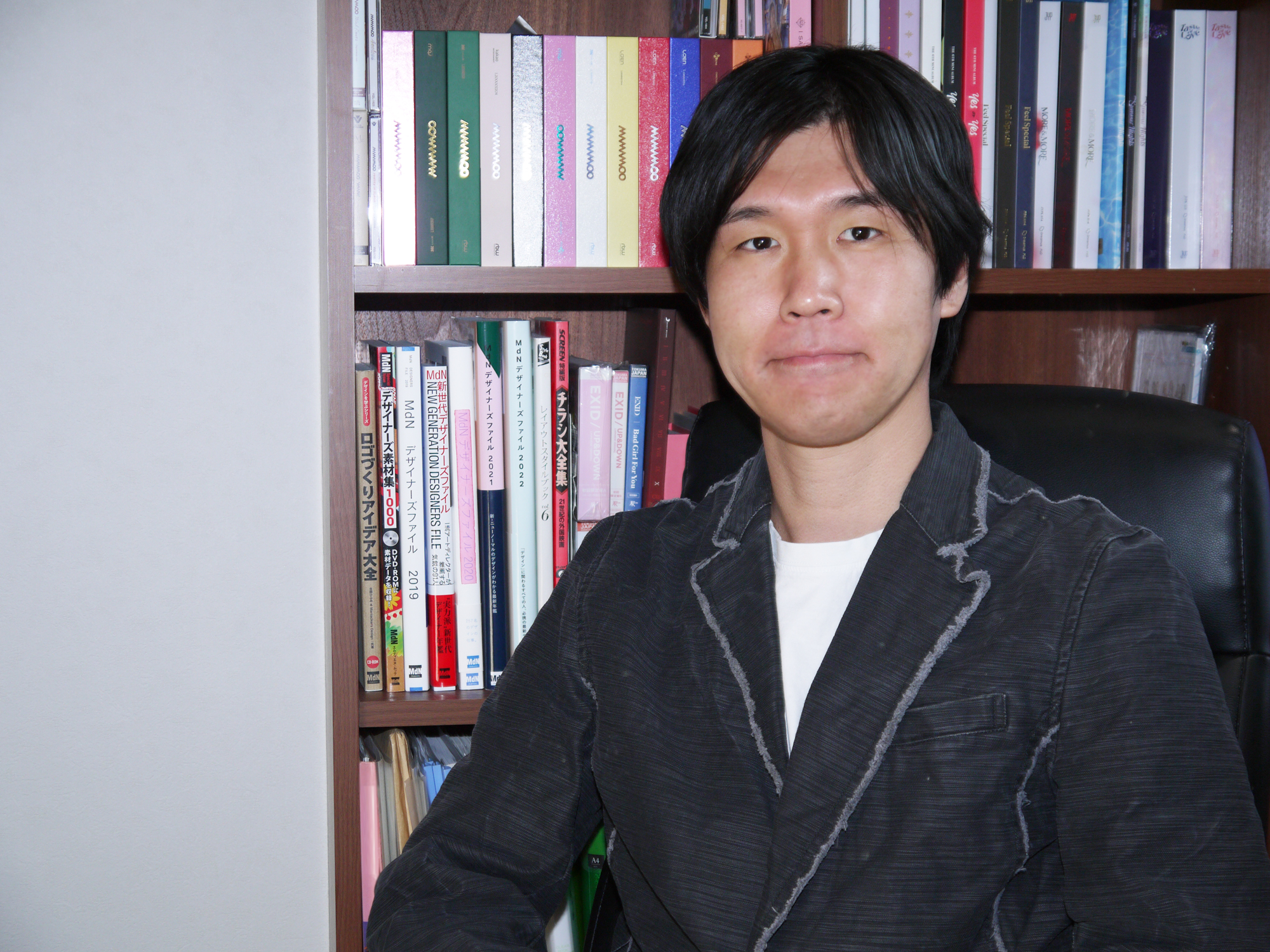
株式会社ウイングフォーム 代表取締役 伊藤友也
広告代理店勤務を経て、地元である埼玉県さいたま市地域の広告物に特化して取り組める環境をと思い、株式会社ウイングフォームを起業。主に企業や飲食店のチラシや封筒、ポスターなどのDTP印刷、ホームページ制作および広告代理業などを行い、地元地域のみならず各地域クライアントが「根差すPR」を目指して展開。会社やお店だけでなく個人の依頼も取り扱い、数量の少ない印刷物や小回りの利くちょっとした制作物を低価格で制作できるよう努めている。